スポーツと選手の意識を高めるための活動
以前、ライターさんより取材を受けておりました内容が記事としてアップされました。
当協会代表理事の中野、及び理事で元千葉ロッテマリーンズ投手の荻野によるコメントが載っています。
当協会の趣旨や概要も記載してありますのでどうぞご覧ください。
▼東洋経済オンラインより引用
https://toyokeizai.net/articles/-/306012
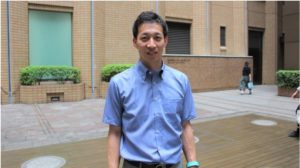
千葉ロッテマリーンズの荻野忠寛(おぎの ただひろ)という投手を覚えている野球ファンは多いのではないか。
いまから10年ほど前にロッテの救援投手として活躍した。
174㎝72㎏という小柄な投手だが、内角をズバッとつく小気味よい投球で、一時期はクローザーも務めた。
引退後、荻野は野球指導者になったが、現在は野球にとどまらず、スポーツと子どものために、幅広い活動を展開して注目を集めている。
荻野は小学2年で野球をはじめ、桜美林高校で本格的に取り組む。体が小さくて、ドラフトにかかるレベルではなかったが、神奈川大学に進み大学2年春からエースに。
頭角を現すもプロからは声がかからず、日立製作所に入る。社会人では過酷な登板を経験し、肩やひじに、かなりのダメージを受けた。
2006年、大学生・社会人ドラフト4巡目でプロ入りする。
プロ通算178試合に登板した荻野忠寛
プロでは、小宮山悟、成瀬善久ら一線級の投手のレベルの高さを目の当たりにして、「手を抜いて投げて通用する投手ではない」ことを痛感し、投球術に磨きをかけた。
1年目はセットアッパー、2年目はクローザーで活躍。
しかし実質的なキャリアは3年(2007~2009年)で終わり、あとは肩、ひじの故障に泣く。
最初の3年で169試合に投げたが、残りの5年で9試合にしか登板(2012年に5試合、2013年に4試合)できなかった。
しかし、荻野にとって、その残りの5年間が非常に有意義だったという。
荻野は2014年に戦力外通告を受けるが、翌2015年から日立製作所に復帰。
この時点で、荻野は独自の「故障しないフォーム」を完成させていた。
日立製作所ではエースとしてチームを創設依頼初の都市対抗決勝戦に導く。
準決勝に終わったが、2016年限りで現役を引退した。
さまざまなレベル、環境で野球をする中で、荻野はスポーツと選手の「意識」の問題を考えるようになった。
プロ野球のトップレベルの選手たちの意識の高さ、試合で見せる集中力、自分で組み立てる合理的で効率的な練習プログラム、そして体のケアにかけるコストと手間暇。
「僕は、野球選手には、たとえ育成枠でチャンスが回ってこなくてもいいから、機会があればプロ野球に行ったほうがいいと思っています。行って、一流の選手がどんな練習をしているか、どんな意識で努力しているかを実感すれば、人間は変わりますし、その後の人生も変わると思います」
それに引き換え、社会人以下のアマチュア野球の知識量の少なさ。意識の低さ。
これでは、アマからいい人材は育たないと痛感した。荻野は技術や知識を教える以前に、「意識」レベルで教えるべきものがあると考えた。
荻野はそれを「スポーツセンシング」と名付けた。
優秀な人は「センス」をもっている
「練習メニューを組み立てる以前に『やる人間のセンス』を鍛えなければどうしようもないと痛感したんです。
大学院などいろいろ探しましたが、どこにもなかったので独学で理論を作りました。
僕は野球で経験したのですが、どんな分野でも優秀な人は『センス』をもっています。
『センスがある人』とは、物事を捉える優れた力と思考技術、知識をもった人のことです。
優れたイメージを作って、そのイメージに自分を引き寄せることができる人、ともいえるでしょう。『センス』がなければ、どんなにいい指導を受けても伸びません。
僕がロッテで接したトップクラスの選手も『センス』があるから、自分を鍛えることができるし、好成績につなげることができました。
そういう『スポーツセンシング』があるアスリートを育てるために、どんな能力を磨くべきか。
そのためにはどんな努力をすべきかを、具体的なプログラムに落とし込んで指導しています」
今、佐賀県の少年野球チームや、東京都町田市など3つのベースボールスクールのアドバイザーを務めている。2017年2月には学生野球資格回復認定も受け、硬式野球だけでなく、高校の軟式野球部、大学の準硬式野球部の指導も行っている。
率直に言って、野球界では荻野のスポーツセンシングに対する理解は「濃淡がある」という感じだ。
素直に荻野の考えを受け入れているチームがある一方で、考え方をなかなか理解できず「荻野コーチこそうちの野球を学んでほしい」と言われることもある。
トップクラスの野球に触れたことがない指導者には難しすぎるという一面もある。
一方で、野球ではないほかのスポーツ分野、さらには「教育」の分野で荻野の考えに共鳴する人が出てきた。

2019年6月、神奈川県横浜市の学習塾・湘南ゼミナールで、中学生を相手に講義を行った。野球の話ではない。
テーマは「同じ勉強で成績が上がる人、上がらない人」。野球、スポーツを「勉強」に置き換え、「センス」を磨くことで成績を上げようという講義だ。
大事なのは超集中状態を作り出すこと
相手は父兄ではなく中学生。
荻野は、パワーポイントの資料をもとに、丁寧に説明する。
同じ先生から同じ授業を受けても、成績が上がる子もそうでない子もいる。
それはなぜなのか?
キーワードは「センス」。
センスを磨くことで、スポーツでも、学校の勉強でも成績を上げることができる。
大事なのは「ゾーン」と呼ばれる超集中状態を作り出すこと。
中学生は一生懸命に荻野の話を聞いている。
話だけでなく、荻野は教室のいすを下げて、紙コップに触れていくゲームも体験させた。
これが超集中状態を身に付けることに役立つのだという。
さらに、荻野は「目標設定ワーク」というチャートを示し、生徒に記入させた。
センスを磨くために必要なのは「目標設定」だ。
目標設定をして、その目標に自分を引き寄せていく。
そういう形で成功への道筋を自分で見つけていくのだ。
菊池雄星や大谷翔平が花巻東高校時代に書いたとされる「マンダラチャート」と原理は同じだろう。
具体的な目標設定をすることで、身に付けるべきスキルや技術が明確になり、努力の方向性が決まってくる。
「湘南ゼミナール」は、あらゆる企業の経営者など、社会の一線で働く人による子どもを対象にしたセミナーを実施している。
その一環として荻野忠寛が呼ばれたのだが、荻野のユニークなスポーツセンシング論は、子どもたちに新鮮なインパクトを与えたようだ。
荻野忠寛は、野球の実技の指導者としても一流だ。
とくに投球術では、ひじに負担を掛けない投げ方を編み出している。スポーツドクターも認める技術だ。
しかし、少年野球の現場を回るうちに、そうした技術やトレーニング法を教える以前の問題として、子どもがスポーツをする「環境」が未整備だと痛感した。
そこで荻野は、一般社団法人スポーツメディカルコンプライアンス協会の設立に参加した。
設立趣意書によると、
とうたっている。荻野忠寛の「スポーツセンシング」の理論も当然、組み込まれていく。

代表の中野司は、元はスポーツマネジメント会社を運営。荻野とは千葉ロッテマリーンズの選手のマネジメントを通して知り合った。
アメリカで育ち、現地の高校野球の経験もあった中野は、帰国後、自分の子どもを少年野球チームに入れようとして愕然とした。
専門的な指導の知識も、トレーニング法も知らない指導者がパワハラまがいの指導を行っている。
とても、子どもを預けるわけにはいかないと痛感し、旧知の荻野らと協会を設立するに至った。
・eラーニング
・ライセンス発給
・スポーツにおける現状の調査、公示
・環境改善に関する研究
・医学的側面によりケガ防止に対するプログラムの構築
・国、地方自治体、政府に対するスポーツ現場の報告、陳情提出
などの活動を通して日本のスポーツ界を変革していく。
野球ひじ治療の第一人者である古島弘三医師(慶友スポーツ医学センター長)も、趣旨に賛同し、特別顧問に就任した。
スポーツを通じて子どもたちの未来を守る
来年の東京オリンピックに向けて、スポーツビジネスを盛り上げる機運は高まっている。
その一方で、スポーツをする子どもたちを取り巻く環境は旧態依然としている。
「勝利至上主義」が横行し、子どもの健康被害は今も続いているのだ。
荻野は日本のトップリーグで活躍した、という貴重なキャリアがある。
困難な道ではあるが、それを単なる「勝利」のためではなく、「スポーツを通じて子どもたちの未来を守る」という異なる目的のために生かそうとしている。
▲東洋経済オンラインより引用








